2024年9月、東京都から発表された「ODAIBAファウンテン(仮称)」プロジェクトをご存じでしょうか?この計画では、お台場海浜公園のエリアに世界最大級の噴水を建設するという壮大な構想が掲げられています。発表直後から、SNSやニュースでもたびたび取り上げられ、関心を集めている話題のプロジェクトです。
「楽しみ!」という期待の声がある一方で、「なぜ噴水?」「本当に必要?」「税金はどうなる?」といった疑問の声も少なくありません。
そこで今回は、この「ODAIBAファウンテン(仮称)」プロジェクトについて、どんな計画なのか、何が注目されているのか、今わかっていることを整理しながら、わかりやすく解説していきます。
※本記事は2025年8月時点の情報です
ODAIBAファウンテンプロジェクトの概要
ODAIBAファウンテンは、高さ150メートルの噴水と、東京都の花である「ソメイヨシノ」をモチーフにした横幅250メートルの噴水を組み合わせた世界最大級の規模の噴水施設です。お台場海浜公園の水域内に設置される予定となっています。
この噴水は、臨海副都心だからこそ味わえる都心の貴重な水辺から、レインボーブリッジや東京タワーなどをバックに展開する噴水ショーを通じて、東京の新たな魅力としてアピールすることを目的としています。
期待が高まるその一方で、いくつか疑問も挙げられているので後ほど詳しくご紹介していきたいと思います。
疑問点1:税金の無駄遣い?26億円の財源は?

「え、噴水に26億円も使うの?」という声、実はネットでも多く見られます。
ODAIBAファウンテンの整備費用は、ざっと約26.4億円。さらに、稼働後の維持管理費として年間1.5~2億円がかかるとされています。
この金額だけを見ると、たしかに「ちょっと贅沢すぎでは?」と感じるかもしれませんよね。
ただし、ここで大事なポイントがあります。
東京都はこの事業について、「都民の税金は直接使っていない」と説明しています。というのも、このプロジェクトの整備費や運営費には、一般会計(いわゆる税金)ではなく、「臨海地域開発事業会計」という特別な会計が使われているからです。
これは、臨海地域の埋立地を売却した収入などを財源とした“特別会計”で、臨海エリアの開発・整備専用に使うお金という位置づけなんです。要するに、「税金で噴水を作っているわけじゃないよ」というのが東京都の主張ですね。
ただし、上記の解釈はあくまで会計上の形式論であり、臨海地域開発事業会計の資金自体は都民の共有財産と解釈することもできます。
都民としては、どの会計から支出されるかではなく、その事業が本当に都民の利益になるかという観点で判断することが重要なのかもしれません。
疑問点2:経済効果98億円の根拠は?本当に元が取れる?
ODAIBAファウンテンの維持管理費だけで年間2億円近くもかかるなら、採算が取れるのか気になりますよね。そこで東京都が発表している経済波及効果の試算を見てみましょう。
| 項目 | 金額・規模 |
|---|---|
| 年間観覧者数(推定) | 約3,000万人 |
| 年間経済波及効果 | 約98億円 |
| 整備工事による経済効果(イニシャル効果) | 約38.5億円(初年度) |
| 就業誘発効果 | 約840人の雇用創出 |
(参考:令和 6 年度お台場海浜公園噴水施設の経済波及 … – 東京都港湾局)
この試算は、お台場で過去に行われた花火イベント時の人流データなどを元に分析されており、年間の経済効果は約98億円とかなりの規模となっています。
年間の維持費が2億円だとしても、それを大きく上回る効果が見込まれていることから、東京都としては「十分に投資価値がある」と判断しているようです。
しかしながら、年間経済効果約98億円というのは、どのような算出方法だったのか気になりますよね。
東京都が発表した「約98億円の経済効果」について、より具体的な根拠を調査した結果、以下の事実が判明しました。
- 外部委託先:一般社団法人日本観光振興協会
- 分析手法:観光庁推奨の経済波及効果計算手法を採用
- 基礎データ:2023年12月開催の花火大会における来場者動向調査
東京都港湾局はODAIBAファウンテンの経済効果の算出として、台場地区への新規来訪者の消費額と、既存来訪者の滞在時間増による消費額をもとに算出しています。また算定には「東京都産業連関表経済波及効果推計ツール」が使用されているようです。
- 新規来訪者:噴水ショーを目的に来る観光客
- 既存来訪者:元々お台場に来る予定だった人が、噴水観覧で滞在延長して追加消費
- 対象期間:2026年4月〜2027年3月(初年度)
- 新規来訪者:255万人(国内日帰り客・宿泊客、海外宿泊客を含む)
- 既存来訪者:852万人(お台場の年間来訪者1,750万人から従業者・居住者等を除外)
- 新規来訪者:2時間滞在を想定し、交通費・宿泊費・土産代・飲食費の平均値を算出
- 既存来訪者:1時間延長分の飲食費(国内日帰り客の低め単価で計算)
ここまで全体の基礎データは示されていますが、具体的な数値の計算途中やツール内部の計算係数は非公開となっています。そのため具体的な根拠となる算出方法を完全再現することは難しいですが、以下より筆者のザックリの計算方法を示しています。
総経済効果 = (新規来場者数 × 新規来場者単価) + (既存来場者数 × 既存来場者単価)
= (255万人 × 2,273円) + (852万人 × 469円)
= 57.96億円 + 39.96億円
= 97.92億円 ≈ 98億円
前提(新規来訪者数や1人あたり追加消費額)がこの通りであるならば、98億円/年は極端に甘い数値ではないように捉えられます。ただし、上記の算出では特別イベント(花火大会)のデータを通常運営に適用して算出しているため、毎日の噴水ショー(1日10回、各10分)との集客力には差があるのではないかと考えられます。
また、下振れ要因(風中止・混雑での消費機会不足・既来訪者の消費上乗せが小さい等)が起きると目減りしますので、推計を下回ることも十分考えられます。
そのため、運営後も定期的な効果測定と透明性のある情報公開が求められるでしょう。
疑問点3:海水ではなく水道水を使用?

「お台場の噴水なら、当然海の水を使うんじゃないの?」
そう思った方も多いのではないでしょうか。実際、当初の計画では“海水を活用”する予定でした。
ところが、2025年2月頃に東京都が方針を一部変更。
最終的には、高さ150メートルの噴水に水道水、横幅250メートルの桜型噴水に海水を使うというハイブリッド方式が採用される見込みとなりました。
「どうして変更されたの?」
理由のひとつは、“水質”の問題です。
東京都の調査では、お台場海浜公園の海水には大腸菌が多く含まれていることが明らかに。特に雨が降ったあとには、通常の数千倍〜数万倍の大腸菌が検出されることもあるそうです。
この数値、実はかなり深刻なようです。
環境省の水浴場基準では、大腸菌が1,000CFU/100ml以上だと「不適」とされており、さらに建築物の衛生法でも噴水などに使う“雑用水”には大腸菌が検出されてはいけないと定められています。
つまり、万が一にも菌を含んだ水が観客に飛んでしまうリスクを避けるため、水道水の利用が必要になったというわけです。
その他にも全ての演出を海水で行う場合、以下のようなリスクも指摘されています。
- 病原菌を含んだ水が飛び散ることで、衛生的なリスクが発生する
- 塩分による“塩害”で、周辺の建物や施設にダメージを与える恐れがある
- 強風時には、噴水の海水が広範囲に飛散する可能性がある
これらを踏まえて、東京都は「高さ150mの噴水は水道水で対応」という判断をしたわけですね。
気になるコストは?
もちろん、水道水を使うなら気になるのはコスト。
しかし、現時点(2025年8月)で東京都は具体的な水道料金の見込みを公表していません。
ただし、安全性や環境への影響を考えれば、この選択は“やむを得ない”という声もあります。
「見た目のインパクト」だけでなく、「周囲への配慮」まで考えられているのは、都市型観光施設としては重要な視点ですよね。
疑問点4:いつ見ることができるのか?

ODAIBAファウンテンは、2025年度末(2026年3月末)完成予定です。
2025年夏頃から本格的な建設工事がスタートし、レインボーブリッジを背景にした巨大噴水がいよいよ姿を現します。
完成後は、午前11時〜午後9時の間に1日10回、各10分間のショーが予定されています。
昼間は青空と、夕方は夕日、夜はライトアップと…時間帯によってまったく違う表情が楽しめそうです。
ただし、噴水の特性上、天候次第でスケジュール変更や中止になることがあります。
- 強風時:風速センサーで噴水の高さを自動制御、またはショーを中止
- 雨天時:ショーは基本中止
- メンテナンス期間:定期的に休止
春は桜型噴水と本物の桜のコラボ、夏は涼しげな水しぶき、秋は夕焼け、冬はイルミネーション…と、四季折々の演出が期待されますね。
疑問点5:どこで見ることができるのか?

ODAIBAファウンテンは、お台場海浜公園の水域内に設置されます。住所で言うと、東京都港区台場1-4周辺の海上です。レインボーブリッジや東京タワーをバックに、夜はライトアップも映えるロケーション。東京湾ならではの絶景と一緒に楽しめるのが魅力です。
噴水ショーは、海辺だけでなく、さまざまな場所から楽しめると予想されます。
- お台場海浜公園の砂浜・デッキ
- 台場地区の商業施設(アクアシティお台場、デックス東京ビーチなど)
- 周辺の高層ホテル・ビル
- 対岸の芝浦や豊洲エリア
- 屋形船やクルーズ船
東京都の試算では、これらの観覧可能エリア全体で年間約3,000万人の来場を見込んでいます。
ちなみにお台場海浜公園へは、以下のような手段でアクセスが可能です。
- ゆりかもめ:お台場海浜公園駅から徒歩約8分
- りんかい線:東京テレポート駅から徒歩約15分
- 都営バス:海01系統などでアクセス可能
イベント時や観光シーズンは、お台場海浜公園付近の駐車場は混みやすいので、なるべく電車などの公共交通機関の利用がおすすめです。
今後の展望と課題
ODAIBAファウンテンは、完成すれば東京の新たな観光名所として国内外から多くの人を呼び込む可能性があります。しかし、その運営や環境面では、まだ解決すべき課題も残っています。
航路への影響
噴水が設置される場所は、海上バスや屋形船が航行するエリアと重なります。
そのため、施設稼働によって航路の一部制限や、運行スケジュールの調整が必要になる可能性があります。現在、東京都は水域利用者や海上保安部と協議が進められ、航路確保や安全運航のためのルール作りを検討されているようです。
環境への配慮
世界最大級の噴水は、そのスケールゆえに周辺環境への影響も無視できません。
東京都は、以下のような対策を計画しています。
- 降雨時や水質悪化時の運転休止による安全確保
- 水質管理の徹底と定期的な衛生検査
- 周辺生態系への影響調査を継続的に実施
安全・環境対策が十分に機能すれば、ODAIBAファウンテンは観光の新たな目玉として、お台場エリア全体の集客力を底上げする存在になる可能性があります。
一方で、維持費や利用ルール、地域との共存といったテーマは、稼働後も継続して注視すべきポイントです。
ODAIBAファウンテンプロジェクトの5つの疑問|まとめ
ODAIBAファウンテンプロジェクトは、臨海副都心を世界に誇る観光拠点へと進化させるための、大胆かつユニークな取り組みです。
総事業費は約26.4億円、年間維持管理費は最大2億円と決して小さくはありませんが、特別会計を財源とし、直接的な税負担を避ける仕組みが整えられています。さらに、東京都の試算では年間98億円の経済波及効果が期待されており、投資としての魅力も十分です。
水源の計画変更や風速センサー導入など、安全性と環境配慮にも力を入れており、完成予定の2026年3月末には世界最大級の噴水ショーが東京湾の夜景をさらに輝かせることでしょう。
このプロジェクトをめぐる議論は、都市開発と市民参加の両面で大きな意味を持ちます。
今後も透明性ある情報開示と対話を重ねながら、ODAIBAファウンテンが東京の新たなシンボルとして多くの人に愛される存在になることを期待します。
—
*この記事は公開情報と分析データに基づいて作成されており、特定の政治的立場を支持するものではありません。*
【参考】

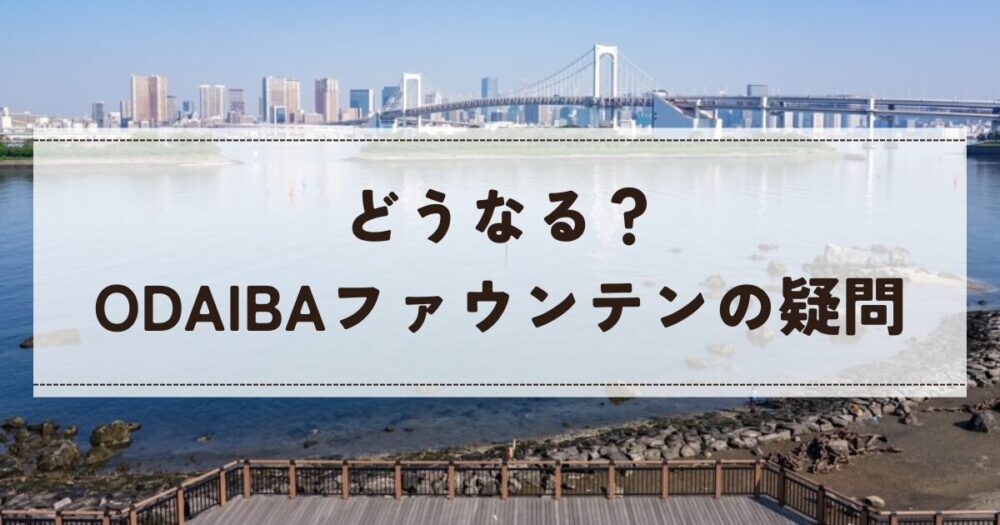
コメント